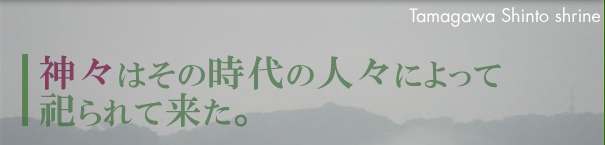

社宝類

薙鎌(なぎがま)
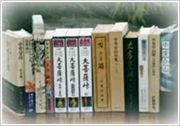
関連書籍
柄鏡(えかがみ) [江戸時代]
棟札(むなふだ) [文化四年・文久三年・明治十五年]
諏訪大社秋宮に建立時の棟札 [昭和四十九年]
薙鎌(なぎがま) [諏訪大社より分与]
古文書類 [江戸時代]
甲源一刀流奉納額 [明治十七年]
中里介山関係文書
由緒
 寿永(じゅえい)年間[一一八二〜八五]武蔵国の武将畠山重忠公の一族が、
古く神功皇后(じんぐうこうごう)の三韓(さんかん)征伐や、
坂上田村麻呂(さかのうえたむらまろ)将軍の東夷平定に神助ありと伝えられ、
東関第一の軍神(いくさがみ)、武士の守護神として尊ばれていた信州諏訪大社より
勧請(かんじょう)したと伝えられている。
もと諏訪宮(すわのみや)、諏訪大明神、多摩大明神とも称した。
寿永(じゅえい)年間[一一八二〜八五]武蔵国の武将畠山重忠公の一族が、
古く神功皇后(じんぐうこうごう)の三韓(さんかん)征伐や、
坂上田村麻呂(さかのうえたむらまろ)将軍の東夷平定に神助ありと伝えられ、
東関第一の軍神(いくさがみ)、武士の守護神として尊ばれていた信州諏訪大社より
勧請(かんじょう)したと伝えられている。
もと諏訪宮(すわのみや)、諏訪大明神、多摩大明神とも称した。天保(てんぽう)年間[一八三〇〜四四]に社家が火災のため、社史の詳細は不明である。 明治二年、諏訪神社と改め、同十五年三月、根岸地区の日枝(ひえ)神社を合祀して、 玉川神社と改称した。このように、創建の当時かた、諏訪信仰に基づいた社であるが、 全国に一万有余社を数えるお諏訪さまは、幅広い信仰を有し、御神徳の数々、 また古くからある信仰には、雨や風を司る竜神(りゅうじん)の信仰や、 水や風に直接関係のある農業の守護神としての信仰が著名である。
また、境内には明治十年代に羽村小学校が建設され、羽村市の学校教育発祥地としても 記念されるべき場所である。
松樹双雀鏡(しょうじゅそうじゃくきょう) [銅鏡] 玉川神社の御社宝
 当社(御祭神建御名方命)の御正体(みしょうたい)として伝えられている。
径十一.五センチ、厚さ八ミリ、二二〇グラムの小型のものである。
中央に鈕(つまみ)があって、その上部に二孔をあけ、向かい合わせて雀を舞わせている。
先年、考古学者の永峯光一先生(三囲神社宮司国学院大学教授)に鑑定をお願いし、
次のような解説文をいただいた。
当社(御祭神建御名方命)の御正体(みしょうたい)として伝えられている。
径十一.五センチ、厚さ八ミリ、二二〇グラムの小型のものである。
中央に鈕(つまみ)があって、その上部に二孔をあけ、向かい合わせて雀を舞わせている。
先年、考古学者の永峯光一先生(三囲神社宮司国学院大学教授)に鑑定をお願いし、
次のような解説文をいただいた。
「松樹双雀鏡(鎌倉期)を利用し、二孔をあけて懸垂し、現世利益を祈願した 信仰的対象物。正式には鏡面に、各種の仏像や種子、各号などを毛彫にしたものが多い。」
恐らく、当社創建時からのものであろう。ちなみにこれと全く類似した双雀鏡が、 諏訪大社秋宮宝物殿に蔵されている。 昭和十年五月に同社東片拝殿の東隣りに接した宝納堂(維新時に除かれた)付近から発掘されたものであるが、 諏訪の御分社であるが故に、何か神縁を感ぜざるを得ない。